

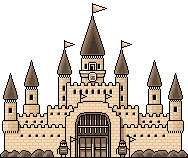
気分転換に旅先(モチロン仕事)での画像をお届けします!
(印象に残った画像を都度掲載予定です)
<2014年の大河ドラマ「軍師官兵衛」> 織田信長、豊臣秀吉、徳川家康。三人の天下人に愛され、恐れられた男、官兵衛。 その類いまれな知略と先見性で戦国の世を駆け抜けた知将・黒田官兵衛孝高(如水)は、 戦乱の世にあって「戦わずして勝つ」を実行した、奇跡の名将といえるかもしれません。 <黒田藩ゆかりの神社 光雲神社> 光雲神社は、福岡藩の藩祖・黒田官兵衛と初代藩主・黒田長政の親子を祀る神社です。 神社の名前は、2人の龍光院殿(如水)、興雲院殿(長政)という法名から 一字ずつ取って名付けられたそうです。    ※中洲/元祖博多ラーメン/博多天ぷらたかお ※久しぶりにリフレッシュできました! |
|
 光雲神社 |
元々は福岡城内本丸天守台の下に作られた 神社だが、明治4年の廃藩置県により 黒田家が東京に移転した際、 現在の警固神社近くに移転されました。 その後、西公園山頂へと移ったそうです。  |
 母里太兵衛の銅像 |
福岡藩士で黒田二十四騎の一人 母里太兵衛の像 右手に持つのは名槍日本号 像の下部には、 「黒田節」の歌碑が刻まれています |
 水牛の兜 |
福岡藩初代藩主・黒田長政が愛用した 水牛の兜は、もともと浦野半左衛門勝元という人 が持ち主で、勝元が長政に仕えるときに献上 したものと伝えられています。 長政はこの兜がたいそう気に入り、 よく着用したようです。 |
 家紋「藤巴紋」 |
荒木村重が織田信長に謀反を起こし、 その説得にあたった官兵衛。 しかし官兵衛は説得する所か 村重の城に閉じ込められてしまいました。 窓の外から見える、日ごとに大きくたくましく 育ってゆく藤蔓(ふじづる)。 そんな藤蔓に励まされ、 つらい獄中生活に耐えていた官兵衛は、 村重の城から出た後、 黒田家の家紋を藤巴に選んだのでした。 |
<ぶらり福岡> 福岡と博多の違いは? 福岡市の陸の玄関口はJR博多駅で、観光客や転勤者の方々は、 福岡市に「博多」と「福岡」という二つの名前があることに戸惑われるかもしれません。 「博多」という地名は、奈良時代の八世紀には登場しますが、 「福岡」は、1600年の関ケ原合戦の功により筑前国主となった黒田長政が、 福崎(現在の赤坂付近)の地に新しく城と城下町をつくり「福岡」と改めたことによります。 それ以後、城下町「福岡」と古くからの商人の町「博多」という双子都市になりました。 福岡市が誕生した翌年の1890年に、 福岡市会(当時の市議会)で市名を「博多市」に変更する建議が出されましたが、 議長裁定の1票差で否決されたことは有名なエピソードです。 ※久しぶりにリフレッシュできました! |
|
 中洲(那珂川) |
<中洲> 那珂川の流れに沿って 北西から南東にかけて 約1キロの細長い地形を呈する。 北東から南西にかけての横幅は約200メートル。 |
 三人舞妓 |
那珂川を挟んで、 武士の町「福岡」と商人の町「博多」が 出会う場所として名づけられた「福博出会い橋」。 その博多側のたもとに立つのが、 三人の舞妓の銅像です。 博多人形師「小島与一」が、大正14年(1925年)に パリ万国現代装飾美術工芸博覧会において、 銅賞を受賞し、 「ハカタ・ドール」として世界に知らしめた 同名の作品がモチーフとなっているものです。 |
 おたふく面(櫛田神社) |
<おたふく面> 2月の節分の日に行われる櫛田宮のお祭りで、 日本一の”おたふく面”が飾りつけられ、 能舞台からは年男・年女・地名士による 豆まきが随時行われます。 |
 博多風神雷神(櫛田神社) |
<博多風神雷神> 拝殿の破風の左右に掲げられている 風神雷神の木彫りは風神が あっかんべぇをして雷神から逃げる様子で ユーモアあふれる博多っ子の気質を表している といわれ ています。 この風神雷神は博多座に展示されている 緞帳のモチーフとなっています。 |
 干支恵方盤(櫛田神社) |
<干支恵方盤> 楼門の天井に吊り下げられていて、 毎年大晦日に新しい年の恵方を示すように 矢印が回転されます。 また、楼門の額「威稜」は「いつ」と 読み天子・天皇の御威光という意味です。 |
 飾り山(櫛田神社) |
<飾り山笠> 博多祇園山笠とは、 福岡県福岡市の博多区で 毎年7月1日から7月15日にかけて 開催される700年以上の伝統のある祭である。 櫛田神社にまつられる 素戔嗚尊に対して奉納される祇園祭のひとつ。 正式には櫛田神社祇園例大祭。 博多どんたくとともに、博多を代表する祭りである。 |
 住吉神社 |
祭神、底筒男神・中筒男神・表筒男神の 住吉三神。式内社。筑前国一宮。 昔の地形は博多湾に臨む那珂川河口の岬だった。 全国に約2000社ある住吉神社の始源と考えられ、 開運除災・航海安全・船舶守護の神 として崇拝されてきた。 |
 楽水園 |
博多区・住吉神社の北側ある日本庭園。 明治時代に建てられた 博多商家の別荘を茶室棟として改築し その中に当時の茶室を「楽水庵」復元したもので、 四季折々の緑と水辺のうるおいに満ちた 甘美な香り漂う美しい日本庭園だ。 当時の博多豪商の優雅さを垣間見ることができる。 |
 石城山 妙楽寺 |
<ういろう伝来の地> 今では名古屋名物の 「ういろう」が伝来したお寺です。 博多の豪商 神屋宗湛・伊藤小左衛門 や黒田藩家臣のお墓もあります。 |
 南岳山 東長寺 |
<弘法大師が日本で最初に開山した密教寺院> 空海が日本で最初に創建したお寺です。 真言密教が東に長く伝わるようにと 祈願されたそうです。 弘法大師が創建したお寺としては 日本で一番古い霊場です。 |
 旧福岡県公会堂貴賓館 |
「第13回九州沖縄八県連合共進会」 の開催に際して、 会期中の来賓接待所を兼ねて 明治43年(1910)3月に建設。 旧公会堂の内、貴賓館は、 数少ない明治時代の フレンチルネサンスを基調としている。 木造公共建物として貴重であり、 国の重要文化財(建造物)に指定。 |
 旧日本生命九州支店 |
明治時代のわが国を代表する建築家 辰野金吾、片岡安の設計により 明治42年(1909)、 日本生命九州支店として竣工。 尖塔やドームを有するなど 小規模ながら変化に富む。 赤煉瓦と白の石材の組み合わせは、 19世紀末に英国で流行したスタイルである。 |