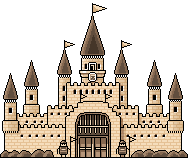<ぶらり石山寺>
石山寺は滋賀県大津市にある 東寺真言宗の寺院です。
琵琶湖の南に位置しており、 国の天然記念物・珪灰石の巨大な岩盤の上に
本堂が置かれていることから「石山寺」という名前になったと言われています。
このお寺が有名な理由の一つが平安時代を代表する作家・紫式部にあります。
紫式部が石山詣で石山寺を訪れた時、作品の着想を得たことから、
紫式部ゆかりの寺として知られるようになりました。
石山寺は平安時代から多くの人々に愛され、色々な作品の中にも登場します。
「枕草子」や「更級日記」・「蜻蛉日記」などにも登場することから、
平安時代より多くの人に愛されてきたことがうかがえます。
  
紫式部が『源氏物語』の構想を練ったことから、
ゆかりの地としても広く知られる湖国の古刹「石山寺」。
花の寺とも呼ばれ、梅・桜・ツツジ・花菖蒲・紫陽花・紅葉などが四季折々で咲き誇り、
訪れる人を楽しませてくれます。
   
※久しぶりにリフレッシュできました!
|

東大門 |
源頼朝に寄進されるも焼失し、
豊臣時代に淀殿によって修理
左右には、鎌倉時代を代表する仏師・運慶
とその長男である湛慶の作と伝えられる仁王像
  |

硅灰石 |
硅灰石は、
石灰岩が地中から突出した花崗岩と接触し、
その熱作用のために変質したもの
「石山」という名称はこの硅灰石に由来しています。
 |

本堂 |
滋賀最古の木造建築物で、
内陣は平安時代中期の建立、
外陣は慶長7 (1602) 年に淀殿の寄進により増築。
礼堂は硅灰石の岩盤にせり出しで建つ懸造
  |

源氏の間 |
新しい物語を書くためこの部屋にこもっていた
紫式部が、8月の十五夜に中秋の名月が
湖面にゆらめく姿から『源氏物語』の構想
を思いついたとされています。
 |

経蔵(安産の腰掛け石) |
県下最古の校倉造りで高床式の「経蔵」
その下に見えるのが安産祈願の「腰掛石」。
 |

鐘楼 |
大きな檜茅葺の屋根と下層のカーブが美しい
鎌倉後期に建立された「鐘楼」、
平安時代につくられた鐘
上層には、無銘であるものの妙音で知られる
平安時代の梵鐘が吊られており、
下層から撞木を引いて撞く
めずらしい構造となっています |

多宝塔 |
建久5年(1194年)に
源頼朝が寄進したと伝えられる
日本最古の多宝塔
上層は円形、下層は方形平面の二重の塔で
上下二層のバランスや軒の曲線の美しく、
日本が誇る最古にして最美の多宝塔 |

月見亭 |
近江八景「石山の秋月」のシンボル
瀬田川の清流を見下ろす高台に設けられ、
後白河天皇以下歴代天皇の玉座とされた。 |

光堂 |
鎌倉時代に存在したという「光堂」を復興。
本堂と同じ懸造となっており、
阿弥陀如来を本尊
 |

八大龍王社 |
龍穴といわれる池の中島に建てられており、
炎天下でも請雨法を修すれば
必ず雨が降るといわれた場所
|

くぐり岩 |
穴をくぐると願い事がかなうとされる
パワースポット
 |

無憂園 |
琵琶湖をかたどった池や滝からなる
回遊式庭園
 |

天智天皇の石切場跡 |
天然記念物「硅灰石」が
道沿いに露出しており、
15か所の採石痕があります。

中央にある矢穴 |