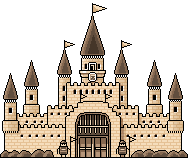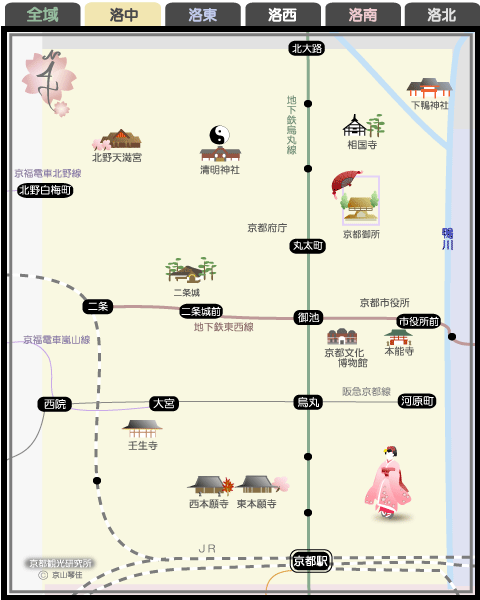<世界文化遺産 二条城>
「元離宮二条城」(二条城)は江戸時代の慶長8年(1603年)、
徳川初代将軍家康が上洛時の宿所としてや京都御所の守護を目的に建てたお城です。
1603年家康が造営した当時、現在の二の丸御殿と天守部分だけでした。
その後、第三代徳川家光が寛永の大改修で二条城の西側に本丸御殿と天守閣を整備し、
ほぼ現在の形となりました。
平成6年(1994年)に世界遺産にも登録されました。
   
※桜が満開でした!
|

東南隅櫓 |
602年から1603年に造られ、
1625年から1626年に改修
二条城には寛永期に建てられた隅櫓が
本来四隅にありましたが、
1788年に起きた大火によって
そのうちのふたつが焼失してしまい、
現在はこの東南隅櫓と
西南隅櫓が残っているだけです。 |

東大手門 |
二条城の正門にあたり、
現在の東大手門は寛文2年(1662年)
に建築されたもの
|

唐門 |
切妻造の四脚門で、
堂々たる唐破風や極彩色の彫刻が特徴。
 |

二の丸御殿(車寄) |
遠侍、式台、大広間、蘇鉄の間、
黒書院、白書院の6棟が立ち並ぶ御殿
部屋数が33、約800畳という広大な空間!

車寄せ欄間 |

二の丸庭園 |
神仙蓬莱の世界を表したといわれる
小堀遠州の手による書院造庭園
 |

天守台から見た本丸御殿 |
本丸御殿は、1893年から翌年にかけ、
京都御苑内にあった
旧桂宮御殿を移築したもの
 |

清流園 |
1960年に作られた新しい庭で、
茶室などがある和風庭園と、
芝生の広がる洋風庭園とに分かれた
和洋折衷の庭
 |

桜の薗 |
二条城のサクラは城内全域で、
約400本・50品種が植えられています
  |