

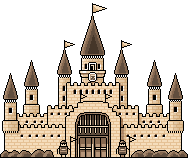
気分転換に旅先(モチロン仕事)での画像をお届けします!
(印象に残った画像を都度掲載予定です)
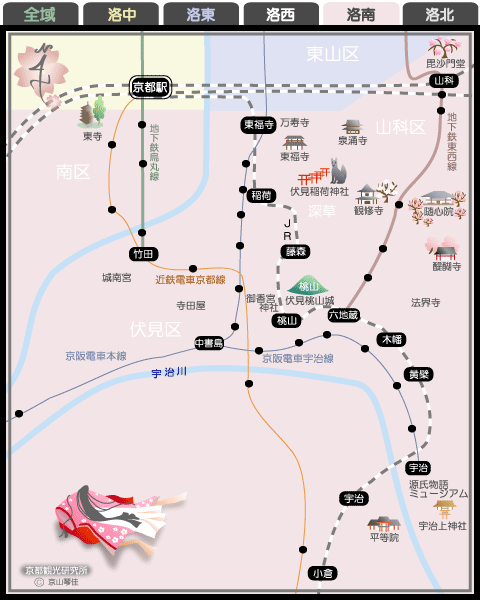 |
<ぶらり醍醐寺> 醍醐寺は真言宗醍醐派総本山の寺院。 伏見区東方に広がる醍醐山に200万坪以上の広大な境内をもち、 貞観16年(874年)に空海の孫弟子・理源大師聖宝が開山・創建したお寺。 874年の創建当時は多くの修験者の霊場として発展していました。 その後、醍醐天皇が醍醐寺を自らの祈願寺とするとともに手厚い庇護を受けたのです。 その圧倒的な財力によって「下醍醐」が発展していったのです。 弘法大師の孫弟子であり修験道中興の祖とされている聖宝理源大師が、 都の東南の方向に五色の雲がたなびいている山を見て、 霊地にすべく登ったところ、横尾明神(醍醐山の神)の化身である老人が現れたという。 老人はそこに湧き出ている水を飲み、 『ああ醍醐味なるかな』と言ったと伝えられており、 これが醍醐寺の名の由来になったとされている。 <五感を澄ませ 僧侶とともに祈る 錦秋の夜> 平成23年より秋期夜間拝観(ライトアップ)が始まりました!    ※久しぶりにリフレッシュできました! |
|
 唐門 |
朝廷からの使者を迎える時に この扉を開けたとされている門で、 中央部の扉には桐、 扉の両側には12個の花弁を有する 菊の花を配している。 この門は慶長4年(1599年)に建造され、 以後、2回移築されているという。 |
 西大門 (仁王門) |
豊臣秀頼が金堂の再建の後、 慶長10年(1605)に再建したもの。 そこに安置されている仁王像(重文)は、 もとは南大門に祀ら れていた尊像で、 平安後期の長承3年(1134)に 仏師勢増・仁増によって造立された尊像です。 |
 金堂 |
醍醐天皇の御願により延長4年(926) に創建された建物。 当時は釈迦堂といわれていましたが、 永仁、文明年間に二度焼失。 現在の金堂は豊臣秀吉の命によって 紀州(和歌山県)湯浅から移築が計画され、 秀頼の時代、慶長5年(1600)に完成 |
 五重塔 |
醍醐天皇のご冥福を祈るために、 第一皇子・朱雀天皇が承平6年(936)に着工し、 第二皇子・村上天皇の天暦5年(951)に完成。 高さは約38メートルで 屋根の上の相輪は約13メートルあり、 相輪が塔の三分の一を占め、 安定感を与えています。 京都府下で最も古い木造建築物となっています。 |
 観音堂 |
この観音堂を中心に広がる、 林泉及び弁天堂、地蔵堂、鐘楼、伝法学院等 を総称して大伝法院と呼びます。 これら諸堂は、醍醐天皇一千年御忌を記念し、 昭和5年(1930)山口玄洞居士の 寄進により造築されたものです。 |