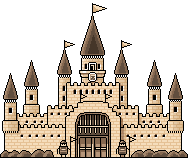�����E������Y�@�Q�A����
�������E�m�a��
���ꂼ��A1994�N12���u�Ós���s�̕������v�Ƃ��āA���E������Y�ɓo�^
��N�P�Q���̋��s�U��Ɉ��������A�P�N�Ԃ�̐��E��Y�U��ł��I
�������̐Β�͖�R�O�N�Ԃ�H�I
����������
�ՍϏ@���S���h�B
1450�N�i��2�j�א쏟�������厛�Ƃ̕ʑ�������A
���S���̋`�V�a�����J�R�Ƃ��T���ɉ��߂��B
�Β�Ƃ��ėL���ȕ���뉀�i�j�ՁE���ʖ����j�́A�O����z�n���Ɉ͂܂ꂽ
�͎R���̕���ŁA�u�Ղ̎��n���̒�v�Ƃ��Ă��B
������15�̐�z��������B
�u�Ղ̎q�n���̒�v��u���O�̒�v�Ȃǂ̕ʏ́B
1975�N�ɃG���U�x�X2�����������������K�₵���ۂ�
�Β���̎^�����̂����������ƂȂ�A
�����̑T�u�[���̌㉟���������Đ��E�I�Ƀu���C�N

���m�a����
�^���@�䎺�h���{�R�B
886�N�i�m�a2�j�A���F�V�c�̒���ɂ��n���A888�N�i�m�a4�j�Ɋ����B
�F���V�c�����������������Ɍ䎺�i������j��݂��A�䎺�䏊�Ƃ��Ăꂽ�B
���̖����Ƃ��Ė������m�a���B
���̎����ɂȂ�ƁA����Ɏw�肳��Ă���
�����̑O�ɂ͐���g��A���O�O�̂�������Ȃǂ��炫�ւ�B
���ł����В��ڂ������̂��u�䎺���v�B
������̐�����тɂ�����т��䎺���̗тŁA�x�炫�Ŕw�䂪�Ⴂ���Ƃ������B

�����e�r�̂قƂ�ɂ��铃��(�������イ=�q��)�����@�ŁA
���{�뉀�߂Ȃ���̓������E�E�E�����������I
|

�������i�R��j |
�؍ȑ��́u�R��v
�R�傪���Ă�ꂽ�̂́A
�]�ˎ��㒆���Ƃ���Ă��܂��B
1755�N�ɍ^���ŗ���ĉ��Ă��܂����̂ŁA
���݂̂��̂͂��̌�̍Č����ꂽ���̂ł��B
|

�������i��j |
��25m�A���s10m��75�قǂ̋�Ԃ�
������~���l�߁A�召�̐��A�����琼��
5,2,3,2,3�ƍ��v15�z�u
  |

�������i�L���F�����j |
�����̐��������̎��Ɍ����Ă��
�u���A�B���A���邱�Ƃ�m��v
����͎߉ނ��������u�m���̐S�v
��}�ĉ��������̂ŁA�����������i
 |

�������i���e�r�j |
�r�Ɏ��̖͂X�����̂悤�Ɉڂ����i����
�u���e�r�v�Ɩ��������A�Ƃ������Ă��܂��B
�����ǂ�̌Q�ꂪ�V�Ԍ��i��
�悭����ꂽ���Ƃ���ʏ́u�����ǂ�r�v |

�m�a���i��j |
���i�`���۔N�ԂɌ����B
��̍��E�ɋ����͎m�������u���Ă���B
��T���O��A�m���@�O��ƂƂ���
���s�O���̂ЂƂ�
 
��̋����͎m�� |

�m�a���i�����j |
����������������ʂɓ��X�ƌ���
����̋����B
���i�N�Ԃ̐m�a���Č��̍ۂ�
�䏊���牺�����ꂽ�����a���ڒz�������́B
�����͐m�a���̖{���ŁA
�{���̈���ɎO�����Ȃǂ����u����Ă���B |

�m�a���i�d���j |
������������ĉE��Ɍ��d���B
���i21�N�i1644�N�j�Ɍ����B
�e�w�̉����̑傫�����قړ����ɑ����Ă���A
�]�ˎ���̌��z�̓�����������Ă���B
������36.18���[�g���B |

�m�a���i�뉀�j |
���a����k���������݂�B
���Ɖ����̌d����
���s��������������B

�얾�a���猩�����a�̒� |