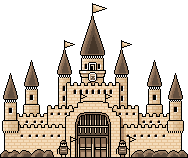���Ԃ���{��
���i�̐��ʂ����啝�ɉ�������i-78cm�j���Ƃ���
2024�N1��4���Ɋ������{�����ݒu����܂���
�i2005�N12���ȗ�18�N�Ԃ肾�����ł��j
����{�遄
�ߍ]������S��̂������q���G�ɂ����1571�N�ɒz���ꂽ���i�ɖʂ�������B
�鋳�t���C�X�E�t���C�X�Ɂu���y��Ɏ����V�����̏�v�ƕ]���ꂽ���s�ؗ�ȏ�ŁA
��b�R�̗}���␅����ʂ̏����߂�v�Ղł������A
1586�N�H�ďG�g�̖��ɂ�肻�̋@�\���Ï�Ɉڂ��p��ɂȂ�܂����B
���i�̐��ʂ��ቺ�������Ƃɂ��
���i�͌ɒ���ł����{��Ղ̐Ί_�̐��p�������Ă��܂��B
�i���i�̐��ꂩ��p�������� �u���̏�v ��{��̐Ί_�j
  
���꒼���ɕ��ԂQ�ӂ̗̐u��{��̐Ί_�v�̍��Ձi���̐Η�j�ł��B
�i�ʐ^�E�F�V�����̍��̐Η�͏M���Ձj
|

��{��̐Ί_ |
���i�͐����ɖv���Ă���
��{��̐Ί_
�i�ł����̕������x���鍪�j
 |

��{��ΔȂ̃��V�Q���n |
�Ί݂Ƀ��V�т��L����
���ӂ̓��V�Q���ۑS���
�Ɏw�肳��Ă��܂�
 |

��{��Ռ������̍��l |
��{�隬�������猩�����i��
�����ō��l������Ă��܂���
���ʂ͎O��R�i�ߍ]�x�m�j
 |

��{��Ռ��� |
��{��Ռ�����
���ۂɍ�{�邪�������ꏊ���
��Ɉʒu���Ă��邻���ł�
 |

���{�������i���g��Ёj |
�����̏㕔�}�̏��
�O�p�`�̔j��������
�R������
 |