

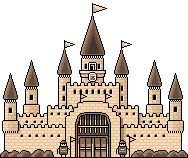
気分転換に旅先(モチロン仕事)での画像をお届けします!
(印象に残った画像を都度掲載予定です)
<ぶらり常滑> 常滑市は、名古屋市から南にのびる知多半島のなかほどの伊勢湾に面した位置にあります。 六古窯の一つとして、平安時代後期からやきものづくりが盛んになりました。 知多半島の豊富な粘土資源や燃料を背景に、発達したといわれています。 <INAX ライブミュージアム> 土は水を得て形となり、火を通してやきものになります。 I2006年、「窯のある広場・資料館」「世界のタイル博物館」「陶楽工房」の既存の文化施設に 「土・どろんこ館」「ものづくり工房」が加わり、やきものの街「常滑」にグランドオープンしました。 さらに2012年、「建築陶器のはじまり館」を新設し、 ものづくりの心を伝えるミュージアムとして躍動感あふれる活動を展開しています。 ※久しぶりにリフレッシュできました! |
|
 窯のある広場・資料館 |
石炭焚きによる両面焚倒焔式角窯 中世の頃から常滑では窯業が栄え、 初めは知多半島の丘陵地という 地の利を活かした穴窯が築かれ、 甕や壷、山茶碗、小皿などを生産していました。 その後16世紀になって大窯に変換し、 江戸時代末の天保5年には、 登り窯が常滑に築かれました。 |
 世界のタイル博物館 |
1991年、タイル研究家・山本正之さんから常滑市へ、 約6000点のタイルの寄贈がな されたことから始まりました。 〈INAX〉は、 常滑市からその管理・研究と一般公開の委託を受け、 1997年に現在の博物館を建設しました。 写真は、ラスター彩獣文星形タイル (イスラームタイル) |
 世界最古のタイル |
緑がかった青色の釉薬が掛かった 縦62mm、横38mmの長方形のタイルです。 この世界最古のタイルは、 今から約4650年前にサッカーラ(カイロの南西25km) に建てられたエジプト古王国時代の 第3王朝期のネチェルケト・ジェセル王の 「階段ピラミッド」の地下にあったものです。 |
 テラコッタパーク |
花や幾何学模様、動物などの彫刻 が施された大きなやきもの装飾「テラコッタ」は、 近代の日本の建築を華麗に飾りました。 今は貴重な文化遺産となったテラコッタに、 青空の下、間近で出会えるのがテラコッタパークです。 写真(左)は、 「横浜松坂屋本館」のテラコッタ(H4.5m×W1.8m) |
 染付古便器 |
江戸時代後期、江戸の町では 藍染めの着物と瀬戸産(愛知県)などの 染付の食器が庶民に広く普及しました。 「青と白」の取り合わせは 粋でお洒落だという感覚が広がり、 人びとにとってあこがれの対象となり 涼しさとみずみずしさの象徴となりました。 |