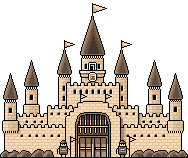<ぶらり上野>
「上野恩賜公園(上野公園)」には、幕末の武士であり、政治家、軍人でもあった
西郷隆盛を讃えることを目的に建立された「西郷隆盛像」があります。
高さ370.1センチメートルの堂々たる体躯で、
しっかりと前を見据える姿は、上野のランドマーク、また東京のシンボルとして
人気を集めるスポットとなっています。
西郷の座右の銘「敬天愛人」
「道は天地自然の物にして、人は之を行うものなれば、天を敬するを目的とす。
天は人も我も、同一に愛し給ふゆえ、我を愛する心を以て人を愛する也」
 
※牡丹の花は「富貴」の象徴で、「百花の王」と呼ばれているそうです。
|

唐門(上野東照宮) |
徳川家康公(東照大権現)をお祀りする神社
家康公の遺言で1627年に創建され、
1651年に三代将軍・徳川家光公の命により
豪奢な建物に建て替えられた。
 |

拝殿(上野東照宮) |
扉部分にはお寺でよく見られる
「法輪」があしらわれており、
仏教と関わりの強い神社であること
を物語っている。
 |

五重塔(上野東照宮) |
上野東照宮の一部として、
1631年に土井利勝によって創建
 |

栄誉権現社(御狸様) |
タヌキは「他抜(他を抜く)」ということで、
強運、受験や就職、必勝の神様
として信仰されている
 |

清水観音堂 |
寛永寺を開創した天海僧正が
京都清水寺を模して1631年に創建
歌川広重が『名所江戸百景』で描いた
松のモデル(月の松)
 |