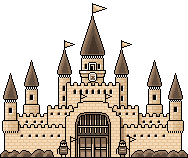<ぶらり宇治>
紫式部と源氏物語ゆかりの町である宇治市。
「源氏物語と宇治」
藤原道長の娘彰子に女房として仕えていた紫式部が
世界に誇る長編小説「源氏物語」を書いたのは平安時代の半ばの1000年頃。
全編54帖のうち44帖までは光源氏を主人公に華やかな宮廷での恋愛模様を描いたものです。
それに対して最後の十帖は光源氏の子薫君と孫の匂宮の二人の男性と
大君、中君、浮舟の三人の姫君が織りなすしっとりとした悲恋の物語です。
その主要な舞台が宇治の地に設定されていることから「宇治十帖」と呼ばれています。
  
※大河ドラマ 「光る君へ」 盛り上げって来ましたね!
|

宇治橋 |
日本三古橋の一つ
上流側に張り出した「三ノ間」は
守護神「橋姫」を祀った名残り
 |

お茶と宇治のまち交流館 茶づな |
光る君へ 宇治 大河ドラマ展
「月夜の陰謀」の中で描かれた
まひろと道長の往復書簡も展示
  |

源氏物語ミュージアム |
源氏物語の粋を集めた博物館
光源氏の邸宅であった六条院の縮小模型や
平安貴族の乗り物や調度品を実物大で復元
 |

宇治川太閤堤跡 |
宇治川の右岸に豊臣秀吉によって
築造された堤跡。水捌けがよいため
茶畑に適しています
 |

宇治上神社 |
世界遺産「古都京都の文化財」
藤原道長の別荘を頼通が1052年に
極楽浄土を再現した寺院に改修
  |

平等院 |
世界遺産「古都京都の文化財」
藤原道長の別荘を頼通が1052年に
極楽浄土を再現した寺院に改修
 |