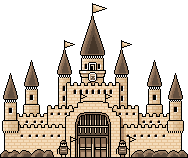<ぶらり柳川>
柳川市は、筑後地方の主要都市の1つ。
市内を掘割が縦横に流れることから水の都と呼ばれ、
筑後地方南西部における商業の中心地であるとともに、鰻料理、掘割を使った川下り、
旧藩主立花氏の別邸「御花」が全国的にも有名。
柳川市は市全体に「堀」が大規模に巡る「水郷のまち」です。
これはもともと海に近い低くじめじめした湿地帯に「堀」を掘り、
掘り起こした泥を盛り上げて乾田をつくり、「堀」は貯水池として生活用水、
農業用水、さらには地下水を涵養し地盤沈下を防ぐなど、
他に代替できない機能で、柳川の人々の生活、柳川土地全体を支えてきました。
柳川の光や緑をそのまま水面に映し、清らかなやさしい水の流れであっても、
力強く私たちを支えてくれる 「堀割」を船頭さんのさす竿に任せてめぐっていく、
ひとときの舟旅が柳川の川下りです。
  
<さげもん>
「さげもん」とは、旧柳川藩時代に女の子が生まれた時、
親戚、知人から贈られた着物のはぎれで、
この子が一生幸せでありますようにと祈りを込めて、
縁起のよい「鶴」「兎」「宝袋」「三番鼠」「這い人形」など
一針一針縫い上げた手作りの布細工と鮮やかな七色の糸で巻いた
柳川地方伝統の大まりを下げ輪の中央に、
小まりと縫いぐるみを交互に下げ輪につりさげたものです。
  
※久しぶりにリフレッシュできました!
|

柳川の川下り |
柳川の川下りは「お堀めぐり」です。
現在の乗船場がある「松月文人館」は、
明治中期の建物で、北原白秋の詩集「思ひ出」
にもうたわれた白秋ゆかりの場所です。
ここから「どんこ船」がゆっくりと漕ぎ出し、
柳川観光の第一章が始まります。
|

御花(松濤園) |
勇将として名高い初代藩主・立花宗茂から
幕末まで、柳川藩11万石を治めた
立花家の歴史が息づく名勝。
元文3年(1738)から「御花畠」と呼ばれる
藩主別邸が設けられていた地に、
明治43年(1910)、伯爵となった
立花家により邸宅と庭園「松濤園」
が造られました。 |

旧戸島家住宅と庭園 |
寛政年間(1789〜)に築造され、
藩公の茶室となっていたもので、
建物は県文化財の指定を受けています。
また築山山水の美しい庭園は
国の名勝に指定されています。
|

白秋生家 |
明治・大正・昭和と生き、
日本の近代文学に偉大な足跡を残した
詩人北原白秋は、代々柳川藩御用達の
海産物問屋を営む旧家に生まれました。
「水郷柳川は、我詩歌の母体である」と述べ、
57才で亡くなるまで生涯柳川を愛し、
数多くのすぐれた詩を残しました。 |