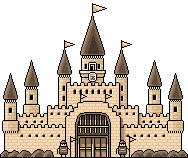<ぶらり平泉>
■世界文化遺産
平泉‐仏国土(浄土)を表す建築・庭園および考古学的遺跡群
(中尊寺・毛越寺・観自在王院跡・無量光院跡・金鶏山で構成される世界遺産)
毛越寺(もうつうじ)
円仁 (慈覚大師) によって850年に開かれたと伝えられる天台宗の寺院
大泉が池を中心とする浄土庭園と平安時代の伽藍遺構が
ほぼ完全な状態で保存されています。
日本最古の作庭書「作庭記」の思想や技法を今に伝える貴重な庭園として、
現在も、なお変わらぬ美しさを見せています。
  
※久しぶりにリフレッシュできました!
|

毛越寺 |
毛越寺最大のみどころは、
平安時代の貴重な浄土式庭園
「毛越寺庭園」です
 |

本堂 |
毛越寺一山の根本道場である本堂は、
平安様式の建物で1989年に建立
 |

開山堂 |
毛越寺を開いた
慈覚大師円仁をまつる堂
 |

蓮池 |
1979年に奈良唐招寺から譲り受け
大泉が池に植えたものの
 |

築山(大泉が池) |
大泉ヶ池の南西の隅、
南大門の西寄りにある築山
池水面より約4メートルほどの高さ
水際から山頂近くまで大小各種の石を立て、
岩山の姿を造り出しています。
|

洲浜(大泉が池) |
池の東南隅に築山と対照的に造られた洲浜
砂洲と入江が柔らかい曲線を描き、
美しい海岸線を表しています
|

出島石組と池中立石(大泉が池) |
池の東南岸にある荒磯風の出島
水辺から水中へと石組が突き出し、
その先端の飛び島には
約2mの景石が据えられ、
庭の象徴として
池全体を引き締めています。
|

遣水(大泉が池) |
池の東北側にある遣水は、
池に水を引き入れるためと造られたもので
平安時代から残る貴重な遺構
「作庭記」に記述されている
四神相応・吉相の順流であり、
曲がりくねる水路の流れに、
水切り、水越し、水分けなどの石組が配置
|