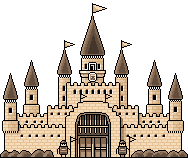<ぶらり金沢>
兼六園を散策!
兼六園下・金沢城のバス停から桂坂を上ると、
左側が「兼六園」、右側の石川橋を渡ると「石川門」です。
<兼六園>
水戸偕楽園、岡山後楽園とならぶ日本三名園の一つ
江戸時代の代表的な大名庭園として、加賀歴代藩主により
「廻遊式」の要素を取り入れながら、
様々な時代の庭園手法をも駆使して総合的につくられた庭です。
<雪吊り>
金沢での冬の風物詩になっている「雪吊り」
湿度のある雪の重みから枝を守るために行います。
雪吊りには「しぼり」「みき吊り」「りんご吊り」の3つの方法がありますが、
代表的な名木には一番複雑で念入りに施す「りんご吊り」を用います。
りんご栽培が盛んだった金沢市で、
大きくなった実を枝折れから守るために行われていたのが始まりだとか。
   
※久しぶりにリフレッシュできました!
|

兼六園(桂坂口) |
日本三名園のひとつに数えられる
兼六園には7つの入場口があります。
すぐそばに桂の大木があることから
名付けらました。 |

噴水 |
日本で最古の噴水
霞ヶ池を水源とし池の水面との高低差による
自然の水圧であがっています。
|

海石塔 |
瓢池の中島に建つ、高さ4.1mの塔
虫が喰ったように穴の空いた
淡茶色の笠石が、
六重に重ねられています。
 |

唐崎松 |
13代藩主・斉泰が近江八景の一つ、
琵琶湖畔の唐崎松から
種子を取り寄せて育てた黒松
雪吊りは兼六園ならではの風物詩です。
 |

雁明治紀念之標 |
中央に日本武尊像
西南戦争で戦死した
郷土軍人の霊を慰めるものです。

両脇に植えられた赤松は「手向松」
|

根上松 |
13代藩主・斉泰が土を盛り上げて
若松を植え、根を深く土で覆い、
成長後に土をのぞいて
根をあらわにしたものだと
伝えられています。
|

雁行橋 |
13代藩主・斉泰が土を盛り上げて
若松を植え、根を深く土で覆い、
成長後に土をのぞいて
根をあらわにしたものだと
伝えられています。
|

黄門橋 |
青戸室石でできた反橋
一枚石を二枚石に見えるよう
立体感を持たせて
細工されています。
|