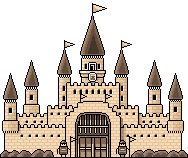<ぶらり 善光寺>
約2ヶ月半の品川出張!
毎週、松本・長野に通い、平日はホテルと会社の往復でした・・・
そこで、午後からの会議の前に少しだけ善光寺詣りです!

<一生に一度は善光寺参り>
善光寺は極楽浄土の入り口、
一生に一度訪れれば、往生がかなうと信じられています。
そして、善光寺は、宗派、男女、貴賤を問わない、無差別、平等のお寺なのです。
だからこそ、全国から参拝者が毎年大勢訪れる日本を代表するお寺の1つであると言えます。
「遠くとも 一度は参れ 善光寺」と謳われ、
“一生に一度お参りするだけで、極楽往生が叶う”
といわれているありがたいお寺だそうです。
※久しぶりにのんびり過ごすことが出来ました!
|

善光寺(仁王門) |
仁王門は宝暦二年(1752年)に建立
されましたが、善光寺大地震などにより
二度焼失し、現在のものは
大正七年(1918年)に再建。
  |

石畳 |
境内地入り口から三門下までの
400メートルに敷かれている石畳は、
正徳四年(1714年)に
江戸中橋の大竹屋平兵衛より寄進。
古来より7777枚あるといわれています。
 |

ぬれ仏(延命地蔵) |
享保七年(1722年)に善光寺聖・法誉円信が
全国から喜捨を集めて造立した延命地蔵。
六地蔵は、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天の
6つの世界で我々衆生を救ってくださる菩薩様
 |

善光寺(山門) |
寛延三年(1750年)に建立された
二層入母屋造りの門。
「善光寺」と書かれた額は、
通称「鳩字の額」と呼ばれており、
3文字の中に鳩が5羽隠されています。
  |
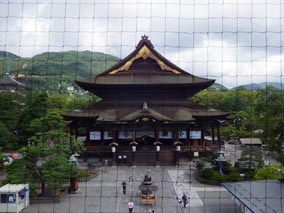
善光寺(本堂) |
江戸時代の宝永4年(1707年)に
5年の歳月を経て完成したもので、
300年の歴史を誇ります。
(撞木造りという独特な建築様式)
  |

善光寺(日本忠霊殿・善光寺史料館) |
戊辰戦争から第二次世界大戦に至るまでに
亡くなられた240万余柱の英霊を祀る、
我が国唯一の仏式による霊廟
|

善光寺(経蔵) |
宝暦九年(1759年)に建立された
宝形造りのお堂。
内部中央には八角の輪蔵があり、
その中には仏教経典を網羅した
『一切経』が収められています。 |

善光寺(大勧進) |
大勧進の住職は貫主と呼ばれ、
大本願の上人と共に
善光寺住職を兼ねています。
貫主は代々比叡山延暦寺より
推挙される慣習になっており、
毎朝善光寺本堂で行われる
お朝事(お勤め)に出仕されます。 |

善光寺(駒返り橋) |
仲見世通りが終わり、
山門へ進む参道の入り口にある石橋は、
建久八年(1197年)源頼朝が
善光寺を参詣した時に、
馬の蹄が穴に挟まってしまった為に
駒を返したという話から
「駒返り橋」と呼ばれています。 |