

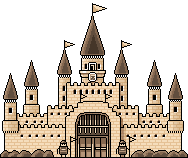
気分転換に旅先(モチロン仕事)での画像をお届けします!
(印象に残った画像を都度掲載予定です)
<ぶらり三井寺> 天台寺門宗の総本山である三井寺(みいでら)は、正式名称を長等山園城寺といいます。 滋賀県大津市、琵琶湖南西の長等山中腹に広大な敷地を有しています。 また、湖国近江の名勝、近江八景の一つ「三井の晩鐘」でも知られています <三井の晩鐘> 近江八景の三井の晩鐘として親しまれている大鐘です。 乳の数が一区内五段五系列の計百個と上帯内部の八個を合わせ総計百八個となっています。 百八煩悩に因んだ数の乳を持つ梵鐘の在銘最古遺品に当たります。 <三井の霊泉> 堂の近くには天智・天武・持統の三帝が産湯に用いたという三井の霊泉があります。 古来より閼伽水として金堂の弥勒さまにお供えされてきました。 閼伽井屋の正面に立ち、三井の霊泉の上部を見ると、立派な龍の彫刻に目が留まります。 この龍の彫刻は、江戸初期の彫刻職人、左甚五郎作と伝えられており、 昔、この龍が夜な夜なびわ湖に出て暴れたため、困った甚五郎が 自ら龍の目玉に五寸釘を打ち込み静めたと伝えられています。 |
|
 本堂 |
 梵鐘(三井の晩鐘) |
 三井の霊泉 |
 龍の彫刻 |
三重塔 |
大門 |
<ぶらり近江神宮> 近江神宮の御祭神・天智天皇は、またの御名を天命開別皇命と申し、 日本の運命を導いてゆかれた御祭神の、万物の運命を開いて行く開運招福の御神徳ことに深く、 時の一瞬の判断が運命を左右することをつかさどり、開運への道を説き示す、 時の神様、導きの神様としての御神徳を合せ持ち、 絶大なる御神威をもって人々の祈りや願いをお聞き届けいただける神様です。 <交通安全祈願> 近江神宮の御祭神・天智天皇は、近江大津宮に漏刻(水時計)を設けて時報を開始された、時の祖神です。 そして先進的な土木技術を駆使して四方八方に道路を開いて行かれました。 「DUALIS」はラテン語で「2元の」あるいは「2つの性質をもつ」という意味。 また、英語の「DUAL」からの造語で、乗る人にONとOFFのデュアルライフでの充実を提供した いという意味も込められているそうです。 |
|
 交通安全祈願 |
 スタイリッシュガラスルーフ |
 |
 |
<ぶらり近江神宮> 第38代天智天皇をまつる近江神宮は、天智天皇の古都、近江大津宮(大津京)跡に鎮座する神社です。 滋賀県西部、琵琶湖西岸の山裾に位置しています。 旧官幣大社・勅祭社であり、社殿は近江造り・昭和造りといわれ、 昭和の神社建築の代表として登録文化財となっています。 開運・みちびきの神、産業文化学問の神として崇敬が深く、 また漏刻(水時計)・百人一首かるた・流鏑馬(やぶさめ)で知られ、 境内に時計館宝物館があり、漏刻・日時計なども設けられています。 |
|
 本殿 |
 楼門 |
内拝殿 |
外拝殿 |
古代火時計 |
内院回廊 |