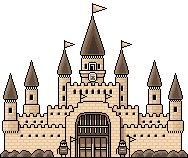<ぶらり烏丸半島(その1)>
滋賀県草津市下物町にある琵琶湖に突き出した半島
草津市域の最北、琵琶湖に突き出す烏丸半島周辺には
琵琶湖の原風景といわれるヨシ原が今もその姿をとどめています。
半島内には日本最多のスイレンコレクションを誇る「水生植物公園みずの森」
「湖と人間」をテーマに見て触れて体験できる「琵琶湖博物館」があります。
また、夏の風物詩となった「熱気球フライト」
「イナズマロックフェス」の開催地としても知られ話題いっぱいのスポットですね。
 
※ノンビリと散策できました!
|

出会いの広場(琵琶湖記念公園) |
「琵琶湖とその水で潤う近畿」
をイメージした出会いのアーチと
石の彫刻12体
 |

琵琶湖博物館 |
世界有数の「古代湖」である
琵琶湖をテーマとする総合博物館
(ビワコオオナマズ水槽は閉鎖中)
  |

水生植物公園みずの森 |
「植物と人、水と人のふれあい」
をテーマにした水生植物公園
スイレンの種類は日本最多の150種類以上
 |

花影の池 |
フラワーバスケットと
水生植物を組み合わせた
ウォーターガーデン
 |

パラグアイオニバス(花影の池) |
1枚の葉の直径は1.5m程
南米パラグアイからアルゼンチン
ボリビアにかけて自生する巨大な水草
 |

アトリウム(ロータス館) |
ハスやスイレンなど
の水生植物を集めており
一年中花が楽しめます。
 |