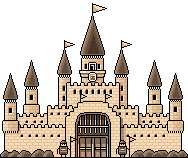<ぶらり奈良>
【法隆寺地域の仏教建造物】【古都奈良の文化財】【紀伊山地の霊場と参詣道】と、
三つも世界遺産に登録されている場所です。
せんとくんは、2010年に奈良県で開催された平城遷都1300年記念事業
(平城遷都1300年祭)の公式マスコットキャラクターであったが、
2011年より奈良県のマスコットキャラクターとなった。
鹿の角が生えた童子の姿をしています。
 
奈良公園の鹿 と せんとくん
※久しぶりにリフレッシュできました!
|

東大寺 |
■世界文化遺産
華厳宗大本山の寺院
奈良時代に聖武天皇が建立した寺
日本各地に建立された国分寺の総国分寺

奈良の大仏 |

春日大社 |
■世界文化遺産
全国に約1000社ある春日神社の総本社
古代の大豪族、藤原氏ゆかりの神社
768年に創設された神社で中臣氏の氏神

御神木 |

興福寺 |
■世界文化遺産
法相宗の大本山の寺院
藤原鎌足と、藤原不比等ゆかりの寺院
古代の大豪族藤原氏の氏寺

南円堂
|

元興寺 |
■世界文化遺産
奈南都七大寺の一つ
蘇我馬子が建立した法興寺が前身とされる寺院
日本で一番古いとされてる「古代瓦」
 
行基葺の瓦 |

浮見堂 |
大正5年に建てられた、
奈良公園の鷺池に浮かぶ
檜皮葺き、八角堂形式(六角形)のお堂 |

旧大乗院庭園 |
大乗院の寛治元年(1087年)創建と
同時に築造された庭園
15世紀の半ばすぎ、善阿弥とその子が
京都から招かれてつくったとされる
|